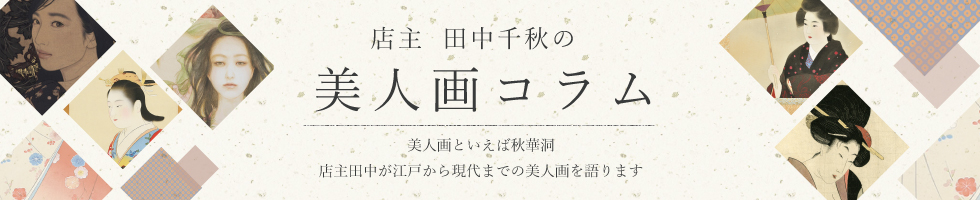
池永康晟は、なぜ好きな女性を絵に描く、ふつうのコトが今の画壇にはないのだろう、という素朴な疑問を持った。日本画で美人画を描こうよ、という運動を興すべく「指の派(ゆびのは)」という名前を作り、仲間を募った。私ども秋華洞は彼自身のオリジナルな運動の賛同者として、アートフェア等で同題での展覧会を行った。
その成果なのか、今は美人画を標榜する若い画家がたくさん出てきた。だが、面白いことに、池永の「美人画」は、深水まで引き継がれてきた「美人画」と同じではない。かつての美人画は、歌麿から深水まで、ほぼ個人の顔は無視されている。むしろ歌麿「美人」、深水「美人」の様式が優先されている。池永のそれは、タイトルにそれぞれモデルの名称が刻まれ、美人の様式そのものよりも、個性が優先されている。そして、絹本か紙本に膠と岩絵の具で描く、といういわゆる日本画の様式も排除されている。麻布に膠を定着剤として褐色の色を置いていく彼の技法は誰にも似ていない。更に言うなら美人画のステレオタイプである「和服」もあまり登場しない。

だが、池永はステレオタイプ的「美人」を避けて、自らの個人史に登場する一人ひとりのモデルを描き分け、自身のリアリティを掴み、鑑賞者の心を掴んだ。彼の「美人画」の成功は、今までの美人画の定義を微妙に外すことで成し遂げられたのだ。その捻じれが、私が面白いと思っているところである。
池永は、画業のはじめから、いわゆる美人画を目指したわけではない。様々なモチーフ、様式を試すなかで、いちばん自分にとって大事なものは何かを見つめることによって今のやり方を見出していった。いつも池永の作品が素朴に心に迫るのは、そうした葛藤の歴史がさりげなく画面に刻み込まれているのを見るものが感じるからではないだろうか。そして池永が感じたふつうのコト。ふつうのコトって、なぜできないのか。実は世の中、「今までこうだった」という群れの中で「ふつうのコト」をやるのは大変なのだ。勇気がいるのだ。それを真剣にやろうとしたとき、道は開ける。
池永はうちが扱ってる若い画家のなかで、もっとも重要と考えている作家だが、彼は今も日々悩み、次の作品へ向かって自ら問い、答えを出していっている。まだ、変わっていくだろう。ふつうのコトをやるために。

秋華洞として二代目、美術を扱う田中家としては三代目にあたります。美術や古書画に親しむ育ち方をしてきましたが、若い時の興味はもっぱら映画でした。美術の仕事を始めて、こんなにも豊かな美術の世界を知らないで過ごしてきたことが、なんと勿体無い日々であったかと思います。前職SE、前々職の肉体労働(映画も含む?)の経験も活かして、知的かつ表現力と人情味あふれる、個人プレーでなくスタッフひとりひとりが魂のこもった仕事ぶり、接客ができる「美術会社」となることを目指しています。
