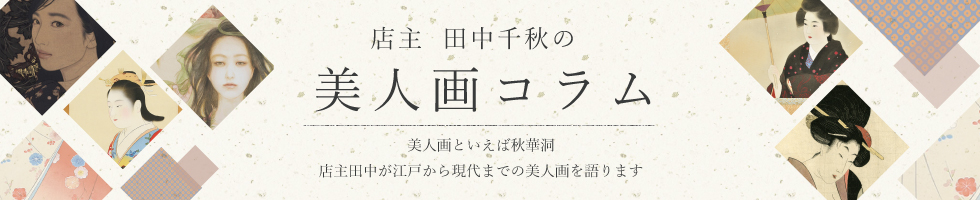
蒼野甘夏が、美人画作家なのかどうか、私にはよくわからない。彼女は、自由画家だと、思っている。トランプのジョーカーが、セブンブリッジや大貧民などのゲームで、なんのカードでも使えるように、彼女は美人画家でもある。そして何より日本画家でもある。
日本画、というのは何となく堅苦しいもの、だと捉えることができる。紙か絹に書かねばならぬ、落款印を押さねばならぬ、裏側に「共シール」を貼ったり、旧きを真似るなら「箱書き」をせねばならぬ、余白が大事だ、いやいや岩絵の具でピカピカザラリと仕上げるべきだ、あの先生この先生がうるさく言う。
花でも人物でも風景でも高尚に仕上げなければならぬ、空気を、音を、気韻生動を伝えねばならぬ、描かなければ日本画の中興の祖、岡倉天心先生が泣く。横山大観が怒る。
そうして、日本画の体系というものは、戦後積み重ねられてきた。むろん、加山又造、中村正義、横山操などの異端児が現れて、引っ掻き回していったし、革新もされた。
だが大学や団体展を占める日本画の多くは、そうした天心以来積み重ねられてきた呪縛から逃れられていないようにも見える。

甘夏は、そんな呪縛を軽々と飛び越えてみせる。日本画は、膠に画材を溶かし、墨をする、というモノグサには面倒くさいプロセスがあるが、それさえも何かクッキングを楽しむように色を溶いていくように思える。
甘夏は、古代人も宇宙人も風景も宇宙も描けるが、私達美術商のリクエストに答えて、チャーミングでちょっぴりセクシーな女性を描いてくれる。ただし「美人」のステレオタイプとは程遠い。だいいち、長い黒髪をたたえたり、結髪の「うなじ」を演出したり、という男目線の趣味とは無縁だ。ショートの女性が、口紅を塗り、キャンデーを口に咥え、絵画空間を自在に飛び回る。
季節の多くを雪に覆われる札幌の地で制作をしながら、彼女の発想と画技は、自由に飛び立つ。
美人画家、と呼ばれれば、そう呼んでも構わない、日本画家、と呼んだって、なんだって、彼女は彼女だ。
そんなことは、どうでもいいのだ。
彼女は、宇宙と人と日本の関係を、性と人との関係を、神話と現代の関係を、膠を溶かしながら、雪面を歩いて買い物にでかけながら、考えている。
彼女の日本画は、「自由」を表象している。日本画は、本当は、堅苦しくない。なんでもできる。自由なんだ、日本、と同じように。そう唄っているのだ。

秋華洞として二代目、美術を扱う田中家としては三代目にあたります。美術や古書画に親しむ育ち方をしてきましたが、若い時の興味はもっぱら映画でした。美術の仕事を始めて、こんなにも豊かな美術の世界を知らないで過ごしてきたことが、なんと勿体無い日々であったかと思います。前職SE、前々職の肉体労働(映画も含む?)の経験も活かして、知的かつ表現力と人情味あふれる、個人プレーでなくスタッフひとりひとりが魂のこもった仕事ぶり、接客ができる「美術会社」となることを目指しています。

