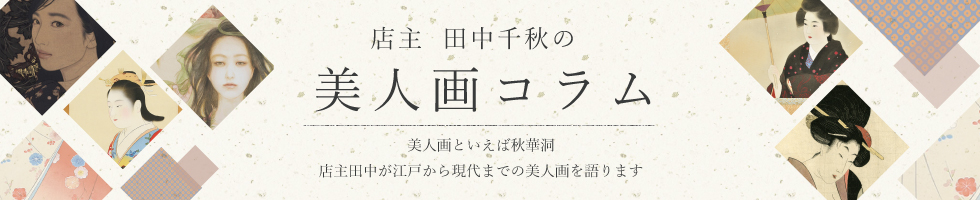
大竹彩奈の画力は21世紀前半の日本画家の中でも屈指だと思う。人物を大きく捉えてデッサンし、強弱の生きた描線を引く。人肌のぬくもりを表現した肌の色、華やかな着物の配色、シンプルだが力強い背景描写など、この10年で池永康晟によって急激に立ち上がってきた「美人画」派とでも呼ぶべき潮流のなかで、頭ひとつ、否ふたつ飛び抜けている。

「美人画」ブームと呼ばれて数年経つが、「美人画」とは無論池永の専売特許でもなければ、ましてや我々秋華洞や諸画廊のオリジナルでもない。おそらくは明治か大正時代に、過去の江戸浮世絵(肉筆、版画)を振り返り、また当時出てきた鏑木清方など、ブロマイド的な女性肖像を総称して出てきたものであろう。言葉として「美人画」が出てきたのは戦後ということらしいが、言葉の成立がなかったとしても、自らをして「美人画」家である、と自認する画家が出てきたのは明治末のことであろう。
ただし、美人画家、というものの立場が高かった時代というものはあまりない。浮世絵美人画を描いていた絵師たちの大半が吉原を舞台にしたものや、春画をこぞって描いていたことからみても、もし「高等」で「超俗」なものがあるとすれば、嘗ては「風景」、今では「抽象」ということになろうか、つまり男の色欲にからみ、俗っぽいものとしての地位を免れないものである。
現代でも事情が似たところがあるが、大竹彩奈はそんな事には目もくれない。自分の信じる美しさ、憧れを描き続ける。それは実の姉の色気、生命力の強さを描くことだ。歌手である姉に和服を着せ、寝床に横たわらせて、男を待つ息遣いをさせる。
しかし、それが淫靡にはならないのは、彼女の構成力の為せる技だ。大竹は、一流で忙しい文学装丁画家でもある。著名小説家や文芸評論家の歴史小説や評論装丁が要求する歴史画や風景画を、たくみに表紙絵として仕上げてしまう。現代画家は実は、小道具、風景など、苦手なものを描くことを忌避しているケースが少なくないが、彼女は現代的美術教育の優等生であり、どんな事物であろうが、ピタリと構成して画面に収めてしまう。女の色気を描かせても、色、形、構成に完璧な着地点を持つ。
資生堂の最高級化粧品のデザインに招かれたのも、商品のコンセプトにきちんと寄り添う仕事が容易に想像できたからであろう。
彼女は多忙でなかなか招くことがかなわないが、私達としては常に彼女の仕事の伴走者でいたいと願っている。
日本画の特徴とされるものが線で何かを表すこととするならば、その「線」の美しさで現代では右に出るものはいないのではないか、と思わせるのが大竹彩奈が女性を描く線である。慎重にさりげなく選びとられた線が、日本女性の色香を余すところなく表現する。日本画という技法がこれほど女性像を描くのにふさわしいものであったのかを改めて気づかされる彼女の作品たちは、まだそのドラマを始めたばかりである。

秋華洞として二代目、美術を扱う田中家としては三代目にあたります。美術や古書画に親しむ育ち方をしてきましたが、若い時の興味はもっぱら映画でした。美術の仕事を始めて、こんなにも豊かな美術の世界を知らないで過ごしてきたことが、なんと勿体無い日々であったかと思います。前職SE、前々職の肉体労働(映画も含む?)の経験も活かして、知的かつ表現力と人情味あふれる、個人プレーでなくスタッフひとりひとりが魂のこもった仕事ぶり、接客ができる「美術会社」となることを目指しています。

