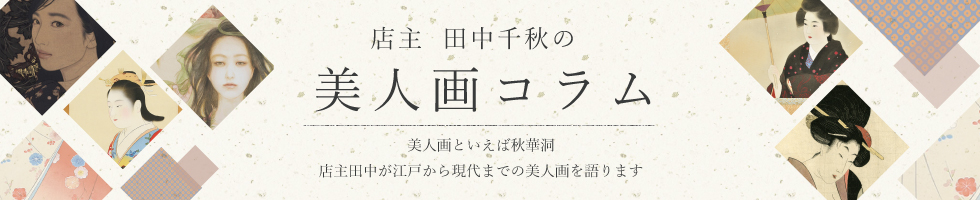
これから美人画のコラムをはじめることにした。
最初に取り上げたいのは、上村松園(うえむらしょうえん)である。
美人画家の代表として上村松園を取り上げるのはごくごく、当たり前のことであるけれども、
私どもは美人画のジャンルに深くこだわりがあるので、松園を美人画絵描きの一押しにするのはあまりにも平凡とも思われる。
しかし、ずっと美人画を扱っていると、やはりこの人をおいて他の美人画家を語っても仕方がない、と思うようになる。
マニアックな美人画の系譜といえば、やはり大阪画壇の甲斐庄楠音、島成園、北野恒富、岡本神草あたりを挙げたくなる。
いずれも大正デカダンの「デロリ」系統の作家と言ってもいい。むろん同じ時代の竹久夢二も思い出すべきだ。
私達が扱う「スター」はこの辺りの名前だ。
けれども。
上村松園がいなければ、美人画は美術業界に席をもらうことはなかった。
ということは言っておきたい。
松園があってこそ、上記の人たちの存在もあったのだ。
松園の作品の持つ緊張感は、他の美人画家と全く違う。
完璧な線。完璧な顔。完璧な色。完璧な箱書き。
私達の職業は、何百点も松園の絵を見ることになるのだが、手を抜いた作品というものが、存在しない。
逆に言えば、他の画家には、良くも悪くも、手を抜いた作品がある。
そして作品の物量。作家が名前を残すには、やはり作品数が必要だ。
松園の凄いところは、クオリティの高い作品が、非常にたくさんあるところだ。
美人画、というのは決して美術鑑賞界において、王道ではない。
もともとフォーマルで権威ある美術界というものがあるとすれば、よりカジュアルで俗っぽい、サブカル的なものだ。
美人画、というものが発生したのは、おおむね江戸時代の歌麿・春信辺りからと言って良いと思うが、
彼らは庶民の味方である「版画」の世界の住人たちだ。
それをメジャーな存在にしたのは、その浮世絵の系譜を継ぐ鏑木清方、伊東深水や竹久夢二であろうけれど、
彼らも初期の仕事は挿絵など、まさにサブカル的な仕事からの出発だ。
その美人画を「俗」でなく「聖」なる存在とし、一大ジャンルとして夜に認めさせたのはやはり松園の力なのだ。
突出しているのである。
何故か男には、どこか仕事に甘いところがある。
この仕事を仕上げたら、一杯飲みに行こうとか、女のところに行こうとか、どこか余計な遊びがある。
その「遊び」がこの二人の仕事の面白み、味であるから、それはそれでよい。
むしろ松園の息ができないほどの緊張感よりも、清方深水のちょっと手慣れた感じがほっとする、という人は少なくない。
けれども、やはり松園に比べると、彼らはちょっと軽すぎるのだ。
王道は彼女に任せた、という気軽さもあるのかもしれない。
何故松園はこれほどの仕事ができたのか。
女だから、ということだけでは片付かない。他にも女の美人画家はいる。
才能は、勿論あっただろうけれど、もうひとつは、彼女をとりまく圧倒的逆境がもたらしたのではないかと思う。
女が仕事をすること自体、どこか偏見と蔑みをもって見られていた時代。
/
そして美人画が一段低く見られていた時代。
そして正式な結婚を一度もせずに子供を一人で育てていた彼女への世間の風当たり。
このすべてを吹き飛ばして、彼女は美人画を画壇の主流に押し上げて、国を代表する画家としての地位を不動とした。
そして彼女にとっては、それは「そうできたらいいなあ」ではなく、そうしなければいけないことであった。
その位、彼女は追い詰められていたのだ。
命がけ。
その精神が彼女の作品、すべてに宿っているのではあるまいか。

秋華洞として二代目、美術を扱う田中家としては三代目にあたります。美術や古書画に親しむ育ち方をしてきましたが、若い時の興味はもっぱら映画でした。美術の仕事を始めて、こんなにも豊かな美術の世界を知らないで過ごしてきたことが、なんと勿体無い日々であったかと思います。前職SE、前々職の肉体労働(映画も含む?)の経験も活かして、知的かつ表現力と人情味あふれる、個人プレーでなくスタッフひとりひとりが魂のこもった仕事ぶり、接客ができる「美術会社」となることを目指しています。

