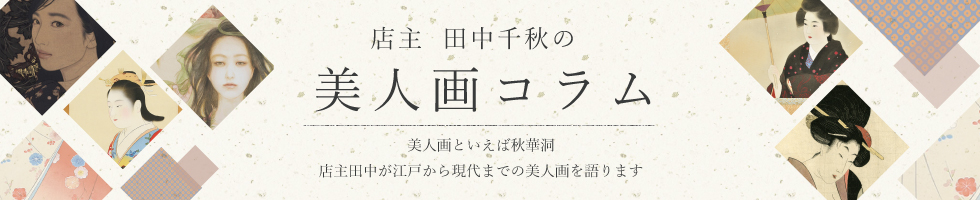
伊東深水は、最後の美人画家、とでも呼ぶべき重要な美人画家だ。
「最後」と呼ぶのには理由がある。我々が推す現代美人画家、池永康晟は、21世紀の日本に新しい「美人画」像を打ち出したけれども、和服美人を日本画で典雅に描くのが近代美人画の定義だとすれば、深水がその完成形を世に打ち出した後、いわゆる「美人画」が中央画壇に場所を占めるのは最後になる。その理由はこうだ。
第一に、それはなんと言っても戦後「和装女性」というものが生活的リアリティを持つものでは無くなっていった事が大きい。「雪に傘美人」的な典型的画題は、江戸の浮世絵から延々続く美人画の「決め」ポーズで、伊東深水の傘美人群が完成形だと思うが、これが生活的リアリティを持つのは深水が亡くなった1972年がギリギリの時代であった。
深水自身も、時代の変わり目を意識して、洋装美人やまた、和服を着ていても洋髪の女性などを好んで描いた。なお、洋髪の方が日本髪の女性よりも若干安いとか安くないとか、絵の相場的な見方で、いまも多少価格に影響はある。
第二の理由。「美人画」の歴史は、「師弟関係」の歴史でも有る。国芳>芳年>年方>清方>深水、という師弟関係で見事に結ばれた浮世絵からの繋がりのある「美人画」は、深水で一旦終焉を迎えた。もちろん、深水の弟子である白鳥映雪、岩田専太郎、立石春美など、様式を引き受けつつ個性を発揮した画家たちもいたし、しばしば深水作品の箱書きをしている浜田台児など、活動はあったものの、深水ほどの巨大な存在には残念ながらならなかったというべきだろう。
美人画の世界自体は、このいわゆる玄冶店(げんやだな)派※だけではもちろんない。菊池契月や小林古径までなかば強引に美人画の仲間に入れればまさに百花繚乱なのだが、いわば一子相伝的(?)な関係性から、「学校」というものに比重が変化したのが私達のいる戦後空間で、なんとなくこのあたりからエネルギーの伝わり方が低くなってきている事も美術体系に影響を与えているようにも思う。
第三の理由について。池永画伯がしばしば指摘するように、写真(グラビア)が「美人」の表象を伝えるのにもっとも重要な位置を占めるようになったことも、深水を最後に美人画が収束していくこととも勿論関係している。
さらには、美術は写真にも映画にもイラストレーターにもできない「なにか」を生み出さねばならない、これは世界的に20世紀の画家に課せられた問題だ。その衝動が熊谷守一や山口長男の抽象表現、もの派や具体美術などの現代アートの流れになっていく。戦後は「美人画」どころか、具象絵画自体が旧くなる時代を迎えつつあった。

さて、深水については、実は版画の仕事も重要で、橋口五葉の版画と同様、評価の高いものも少なくない。版画というのは複雑な評価体系で、ごく近年まで複製的版画も作られているので、何百万もする版画と1万円の版画の「違い」を理解するのは容易ではないが、大正から昭和にかけて作られた渡邉版画など版元の本気度の高いオリジナル版画は、しばしば高値で取引されている。なお、彼には風景画の版画も肉筆もあり、なんでもこなした当時の美人画家の実力をうかがい知ることができる。
ヌードダンスの舞台裏を描いた大作「戸外春雨」や、洒落た人物画など、画技が広くモダンで華やか、芸能界などの付き合いも広く「お金持ちの美術」的な余裕は、おっとりした愛娘、津川雅彦の配偶者・女優朝丘雪路に血が受け継がれているようにも思うが、この大正から昭和40年代までを貫く日本の「洒脱」のようなものは、いったん日本から深水の命とともに姿を消してしまったのかもしれない。「美人画」の時代のいったんの終焉は、「美人画」が引き連れていた日本的「粋」の体系のいったんの終息と結びついている。
さて、令和を迎えた私達の時代。深水という最後の神殿の脇に打ちひしがれた美人画や作家たちの瓦礫や死骸のようなものから、あらたに養分を吸って出てくる「現代人物画」が、そうした過去を乗り越えてあたらしい命を獲得していくのか、私達は、ほんとうの時代のリアリティをつかめるのか。深水を仰ぎ見つつ、<美人画>と私達は、活動を続けるのである。
※玄冶店派:玄冶店とは江戸の日本橋界隈、幕府の医師、岡本玄冶が住んでいた屋敷跡で、絵師や役者が多く住み、一大文化圏を形成していた場所だった。そこに住んだのが国芳で、芳年が弟子入り、後に水野年方-鏑木清方-伊東深水というここからの系列を玄冶店派と呼んだ。

秋華洞として二代目、美術を扱う田中家としては三代目にあたります。美術や古書画に親しむ育ち方をしてきましたが、若い時の興味はもっぱら映画でした。美術の仕事を始めて、こんなにも豊かな美術の世界を知らないで過ごしてきたことが、なんと勿体無い日々であったかと思います。前職SE、前々職の肉体労働(映画も含む?)の経験も活かして、知的かつ表現力と人情味あふれる、個人プレーでなくスタッフひとりひとりが魂のこもった仕事ぶり、接客ができる「美術会社」となることを目指しています。

